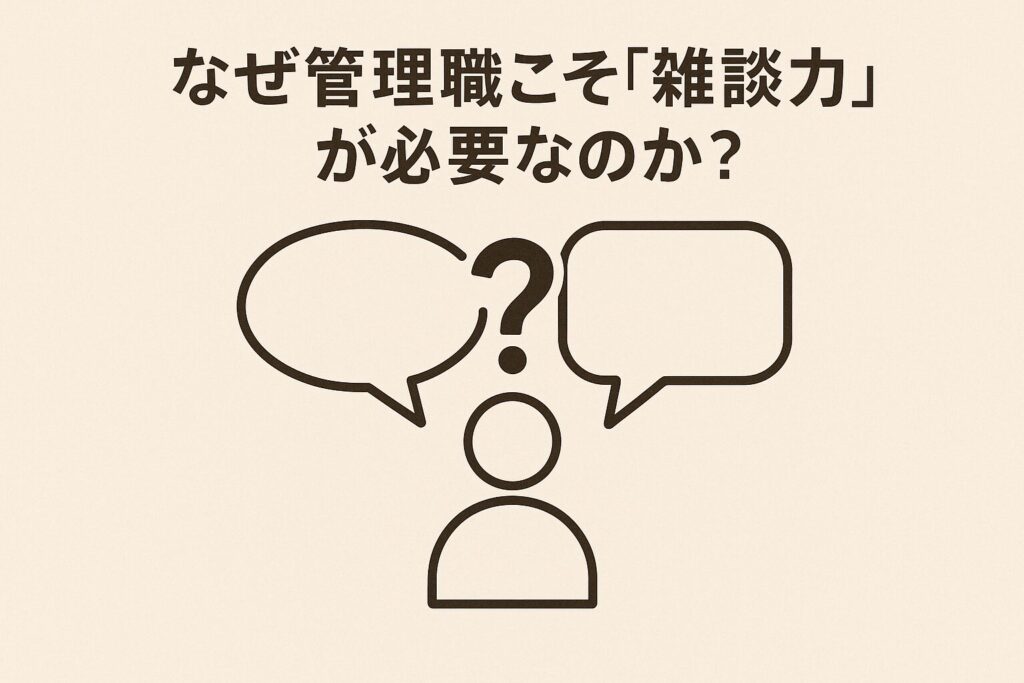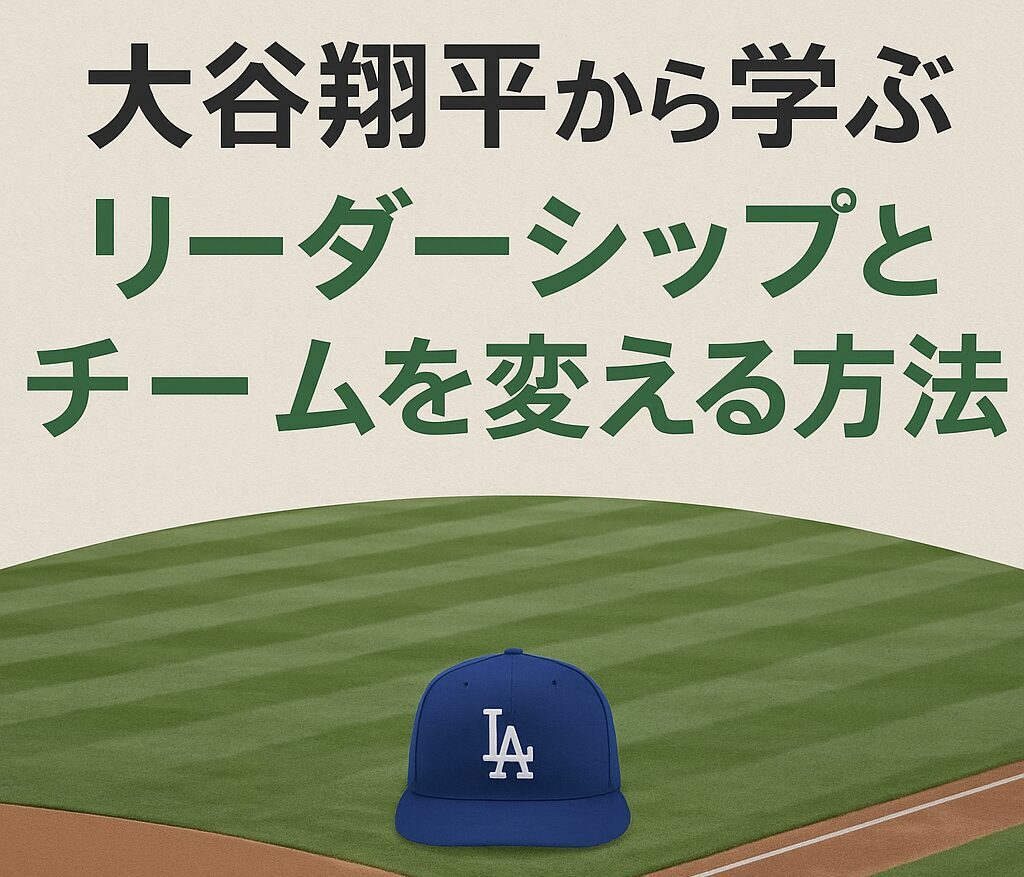はじめに
ビジネスの世界で真の成果を出す管理職に必要なのは、専門知識だけではありません。人と人をつなぐ「雑談力」こそが、チームの潤滑油となり、組織の壁を溶かす重要なスキルなのです。私自身、プレゼンや会議では堂々と話せるのに、廊下で部下と何気ない会話をするのが苦手でした。しかし、五百田達成氏の「超雑談力」との出会いにより、雑談の本質を理解し、実践することで、職場の雰囲気が驚くほど変わってきました。今回は、管理職として組織をより良くするための「雑談力」の本質と実践法をお伝えします。
なぜ管理職こそ「雑談力」が必要なのか?
多くの管理職は「雑談」を無駄な時間と考えがちですが、実はこれは大きな誤解です。雑談の本質は「人間関係の構築」にあります。特に管理職の立場では、チームメンバーとの信頼関係を築き、心理的安全性を確保するために、この「微妙な間柄の人と、会話を通じて人間関係を構築する」スキルが不可欠なのです。
管理職が身につけるべき「超雑談力」の5つの実践法とは?
効果的な雑談は、特別な才能ではなく、習得可能なスキルです。以下に管理職として特に意識したい5つの実践法をご紹介します。
1. 会話のラリーを続けることに集中する
完璧な話題や面白い話を探す必要はありません。大切なのは会話を途切れさせないこと。質問を投げかけ、相槌を打ち、相手の言葉を受け止めるという「ラリー」を意識しましょう。特に部下や新しいチームメンバーとの会話では、この「ラリーを続ける」という意識だけで、雑談の質が大きく変わります。
2. 情報交換ではなく、気持ちのやり取りを意識する
多くの管理職は「情報の伝達」に焦点を当てがちです。しかし、雑談の本質は「気持ちのやり取り」にあります。「このプロジェクトについてどう感じている?」「新しいオフィスの環境はどう?」など、感情や個人的な体験を共有する質問を心がけましょう。
3. 「なぜ?」より「どう?」で質問する
「なぜその方法を選んだの?」ではなく「その方法を選んだ時、どんなことを考えたの?」というように、「どう?」で質問することで、相手に防衛的にならず、気持ちを自然に表現してもらいやすくなります。これは1on1ミーティングでも非常に効果的なテクニックです。
4. 自己開示のバランスを取る
良い雑談には適度な「自己開示」が必要です。「3割自分の話、7割相手の話」を目安に、自分自身の経験や考えも共有しましょう。一方的に質問するだけでは、尋問のようになり、相手に不信感を与えかねません。特に管理職は「自分の弱みや失敗談」を適度に共有することで、より人間的な関係性を構築できます。
5. 「最近どう?」ではなく具体的な質問をする
「最近ハマっていることは?」「休日は何をして過ごした?」など、答えやすく具体的な質問で会話を始めると、相手も話しやすくなります。特に「過去/現在/未来」という時間軸を意識した質問は、会話を広げやすくなるテクニックです。

管理職が「超雑談力」を高める日常の習慣とは?
雑談力は日々の小さな実践の積み重ねで磨かれます。以下に管理職として取り入れやすい日常習慣をご紹介します。
朝の「一言プラス挨拶」を習慣にする
「おはようございます」だけでなく、「今日は良い天気ですね」「その服装似合いますね」など、一言プラスの挨拶を意識的に行いましょう。この小さな習慣が、徐々に自然な雑談へと発展していきます。
「聞く」姿勢を持つ
良い雑談の基本は「聞く」姿勢です。特に管理職は「知らないことを教えてもらう」という謙虚な姿勢で部下の話を聞くことで、相手の自己肯定感を高めると同時に、貴重な現場の情報も得られます。
褒められたら素直に受け取る
日本人は褒められると「いえいえ、そんなことないです」と謙遜しがちですが、これは会話を途切れさせる原因になります。「ありがとうございます」と素直に受け取り、さらに関連する話題を展開させると、雑談が自然に続きます。

まとめ:雑談は管理職の「戦略的武器」である
雑談は単なるおしゃべりではなく、人間関係構築のための重要なコミュニケーションツールです。特に管理職にとっては、チームの信頼関係を強化し、心理的安全性を高める「戦略的武器」とも言えるでしょう。
完璧を目指す必要はありません。まずは「会話のラリーを続ける」という意識から始め、少しずつ自分なりの雑談スタイルを確立していきましょう。組織の壁を溶かし、チームの潜在能力を引き出す「超雑談力」が、あなたの管理職としての新たな強みになるはずです。