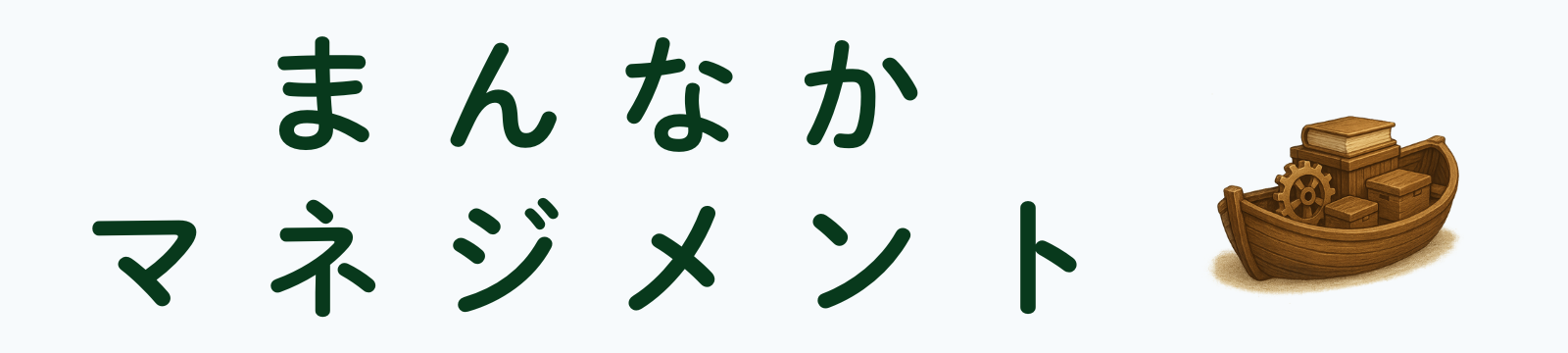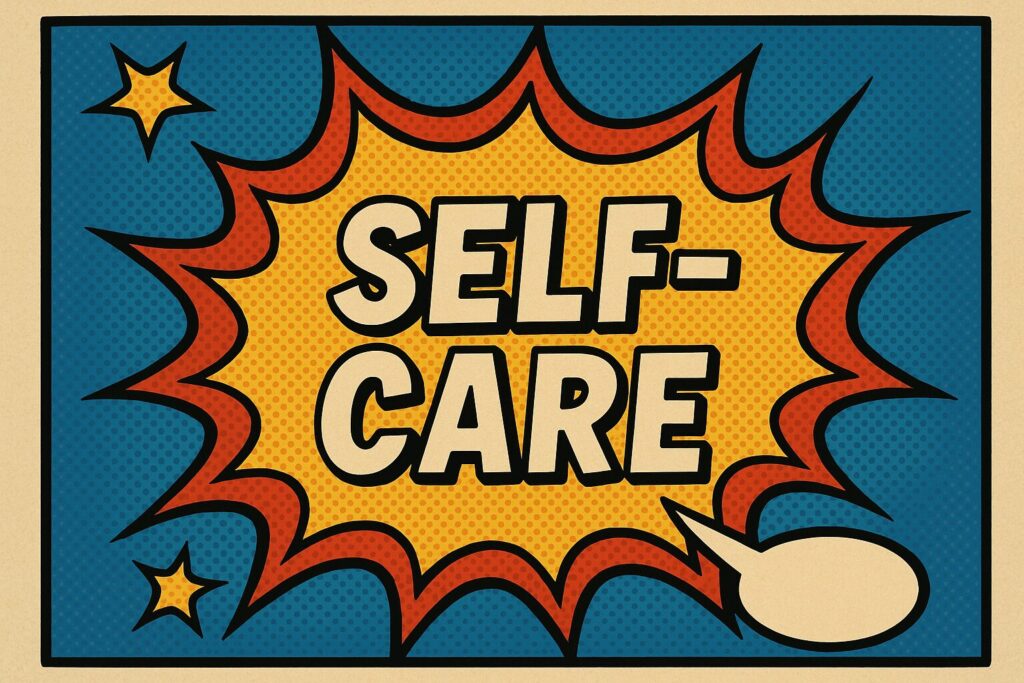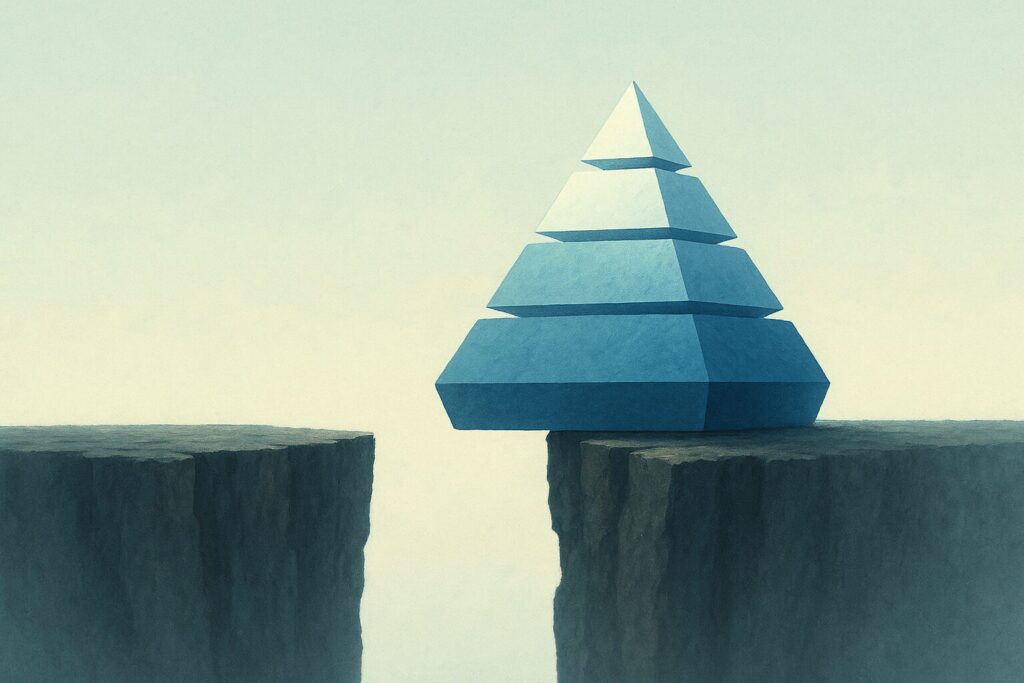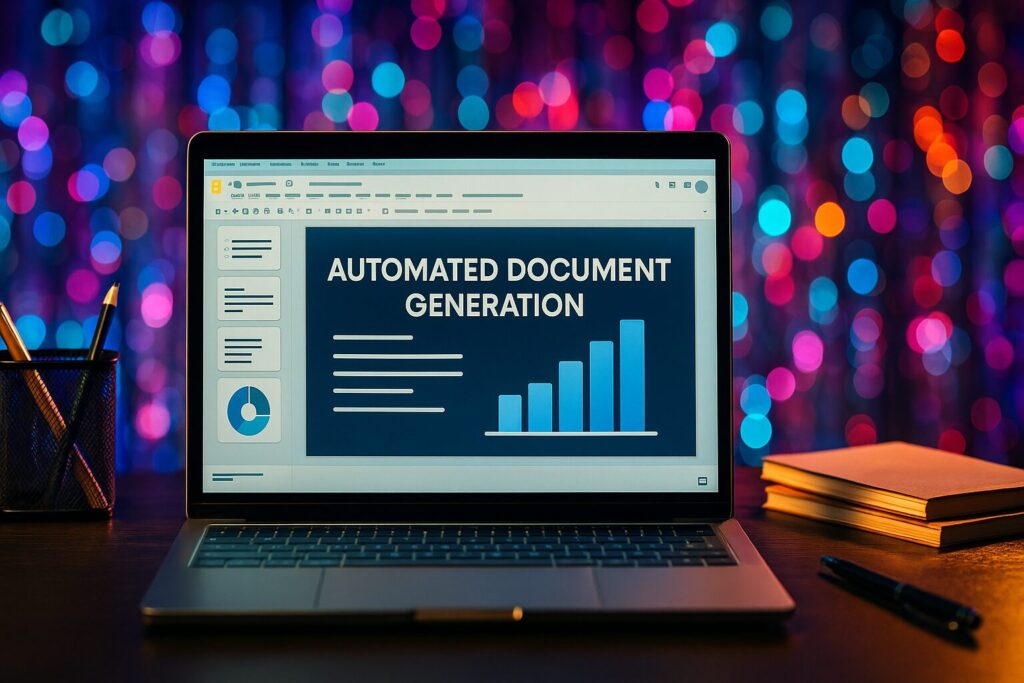―― 学びを通して見えた「自分を整える5つの視点」
医療マネジメント認定士の学習を進めるなかで、「良いケアをするには、まず自分が安定していることが大前提だ」と改めて感じました。
現場で日々人と関わり、感情の起伏に向き合う私たちにとって、セルフケアは決して特別なことではなく「働き続ける力」を支える基礎だと思います。
この記事では、学びと自分自身の経験を重ねながら感じた5つのセルフケアの視点を整理しました。

自分を整える5つの視点
拒否の裏にある「感情」を理解する
リハビリをしていると、「拒否」されることが少なくありません。
以前の私は、「自分だけが拒否されているのでは」「嫌われているのでは」と落ち込みました。
けれど時間が経って冷静に振り返ると、逆に「自分だけが関われる方」もいたのです。
その経験を通して気づいたのは、拒否には必ず理由があるということ。
不安、恐怖、悲しみ――どれも人間として自然な感情です。
相手の感情に共感できたとき、初めて本当の意味で寄り添えるのかもしれません。
「拒否」は拒絶ではなく、感情を共有するチャンスだと今では思っています。
無理をしない ― 「まぁいいか」と思える余白を
医療現場では「頑張ること」が前提になりがちですが、私は無理をしないことを意識しています。
眠かったり、体力的にしんどいときは、どうしても相手に優しくなれなかったり、拒否に対してモヤモヤしてしまう。
そんな自分を責めるよりも、「今はそういう状態なんだな」と受け止めるようにしています。
自分の中の“当たり前”を押し付けず、「まぁいいか」と力を抜ける余白を持つ。
それが、感情に呑まれないセルフケアの第一歩だと感じます。

完璧を目指さない ― 「自分なりの60点」を見つける
テキストの「100点を目指さない」という言葉が印象に残りました。
ただ、実際には“60点でいい”と言われても、その基準は人それぞれで難しいものです。
私自身は、自分の疲労度を一つの目安にしています。
「今日はしんどいけど、最低限やれた」ならそれで合格。
完璧主義は一見美徳に見えますが、現場では燃え尽きを招きます。
大切なのは、長く続けるための“加減”を知ること。
完璧ではなく、継続できるケアを目指すことが、マネジメントの実践にもつながるのだと思います。
柔軟に考える ― 決められない自分も受け入れる
私はINFJという性格傾向もあり、物事を俯瞰して見ることが多いです。
多くの考えを理解できる分、「どれが正しいのか決められない」という苦しみを感じることもあります。

そんなときは、考えを抱え込まずに外に出すようにしています。
自分のアイデアをChatGPTに話して整理してもらうのもその一つ。
「自分の中に閉じ込めないこと」が、結果的に気持ちを整える手段になっています。
柔軟さとは、すべてを解決する力ではなく、「迷いながらも動ける力」だと今では思います。
感情をコントロールしようとしない
感情はコントロールするものではなく、気づいて観察するものだと学びました。
怒りや不安を感じたとき、「なぜそう感じたのか?」と一歩引いて見つめてみる。
そうするだけで、感情に飲み込まれにくくなります。
感情を無理に押さえつけるのではなく、「今の自分」をそのまま認める。
これもセルフケアの大切な一部です。
そして、もし感情が自分の力では抱えきれないほど強くなったときは、専門家に相談することも一つです。
それは「弱さ」ではなく、「自分を守る行動」だと思います。
まとめ
ケアの質は、提供者の安定に支えられています。
拒否の裏にある感情を理解し、無理をせず、自分なりの基準で進む。
そして、感情を手放す勇気を持つこと。
セルフケアとは、「自分を人として扱う力」。
それが、他者を支える“マネジメントの原点”です。