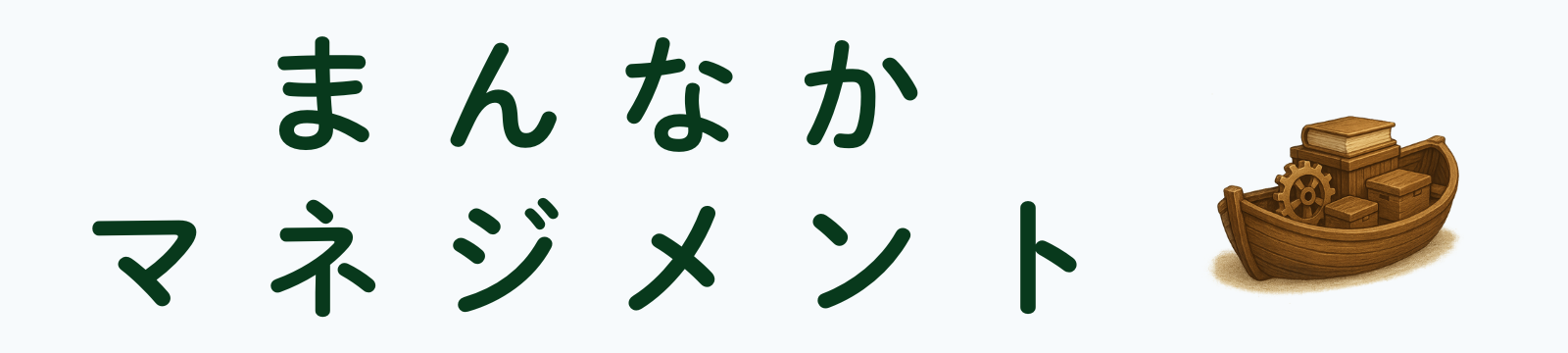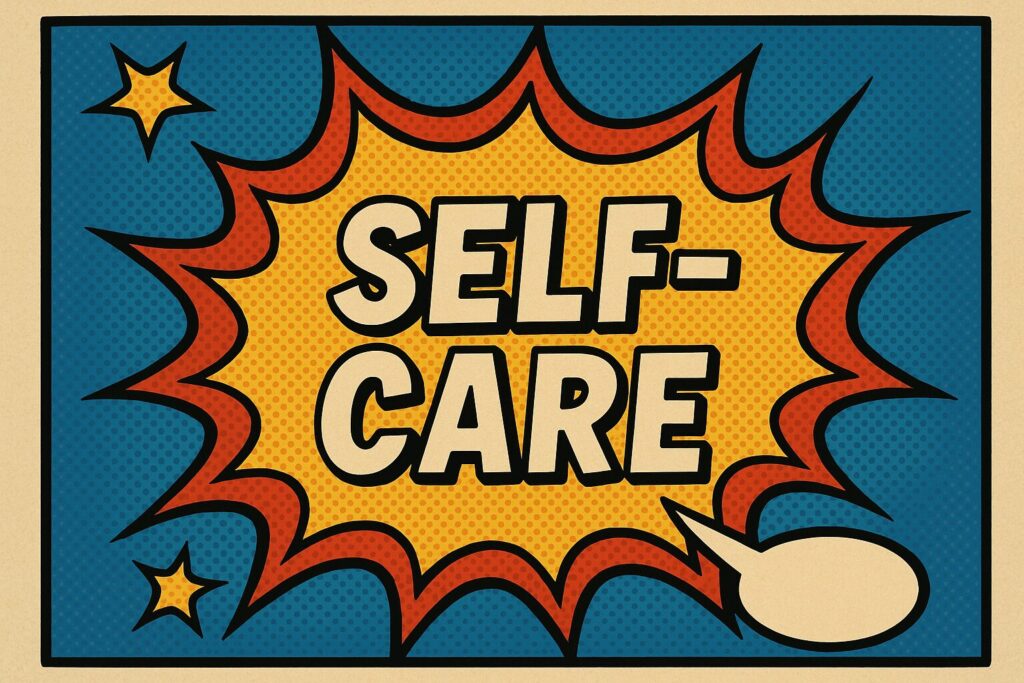管理職になって3ヶ月。正直、毎日が不安でした。「部下をうまく指導できるのか?」「自分はこの役職にふさわしいのか?」そんな思いに押しつぶされそうになった時、偶然手に取ったのが、しんめいPさんの著書『自分とか、ないから。』です。
この本に出会ってから、管理職として「頑張りすぎない」「自然体で成果を出す」マネジメントのヒントを得ることができました。今回は、仏教や老荘思想に基づいた“東洋哲学的マネジメント術”を、自身の経験とともにご紹介します。
管理職が最初にぶつかる3つの壁
1. 組織の成果へのプレッシャー
プレイヤー時代は、自分の努力がそのまま評価につながっていました。でも管理職は「チーム全体で成果を出す」ことが求められます。「自分だけでは限界がある」と気づいた時、何をどうすればいいのか分からず途方に暮れました。

2. 部下との距離感に悩む
指示を出しすぎると煙たがられ、放っておくと頼りないと言われる。この“ちょうどいい距離”がわからずに毎日悩んでいました。部下のミスは自分の責任になるため、「どこまで任せて、どこまでフォローすべきか」判断に迷う場面が続きました。
3. 「自分には向いていないのでは?」という不安
「もっと適任の人がいたんじゃないか…」そんな風に思うこともありました。とくに優秀な同期と比べてしまうと、自分が管理職であることに自信が持てず、どんどん自己評価が下がっていきました。

仏教思想に学ぶ「頑張れない自分」を受け入れる力
親鸞の「悪人正機」が教えてくれたこと
親鸞の思想の中に「悪人正機(あくにんしょうき)」という言葉があります。「善人でさえ救われるなら、悪人はもっと救われる」という考え方です。完璧である必要はない、むしろ未熟さを持っているからこそ学びがある——この言葉に救われた思いでした。
管理職としての「弱さ」を認める
実は、優秀なリーダーほど自分の未熟さに敏感だと言われています。すべてを自分で背負おうとするのではなく、「助けてもらう力」を身につけることも、大切なスキルだと気づきました。
「他力本願」——チームに頼るマネジメント

「他力本願」は誤解されがちですが、本来は「大きな力に身をゆだねる」という仏教の教えです。「人に頼る=甘え」ではありません。
| 従来の考え方 | 東洋哲学的マネジメント |
|---|---|
| 部下のミスはすべて自分の責任 | チームで支え合うのが当然 |
| 上司は完璧でなければならない | 弱さを認め、助けを求める |
「自分がなんとかしなきゃ」は卒業して、周囲の力を借りながら進む方が、結果的に良い成果を生みます。
老荘思想に学ぶ「流れに任せる」リーダーシップ
「無為自然」でコントロールを手放す
老子の言葉に「世界で最も柔らかいものが、最も硬いものを支配する」という一節があります。これは、「無理にコントロールするよりも、自然の流れに従った方がうまくいく」という意味です。

部下を“管理”しすぎない勇気
かつての私はすべての業務に口を出し、部下の失敗を恐れてチャレンジの機会すら奪っていました。今は「信頼して任せる」「失敗も学びに変える」ことを大切にしています。その結果、チームの主体性が高まり、私自身もずいぶん気が楽になりました。

東洋哲学を“毒”にしないために
ただし、東洋思想に頼りすぎると「成長しなくていい」「努力は無意味」という誤解にもつながりかねません。
- 「努力しなくていい」ではなく、「無理な努力はしなくていい」
- 「ありのままの自分でいい」ではなく、「成長しながら自分を受け入れる」
- 「自然に任せる」だけでなく、「判断すべきことは自分で決める」
このバランス感覚が、自然体のマネジメントには欠かせないと実感しています。
自然体で成果を出すマネジメントは可能です
「管理職失格」と思う自分を受け入れる(仏教思想)
「自分一人で背負わなくていい」と考える(他力本願)
「部下を管理しすぎない」ことで成長を促す(老荘思想)
「バランスを取る」ことを意識する
管理職になって感じたプレッシャー、不安、自信のなさ——それらに対して、「完璧じゃなくていい」「人に頼っていい」「自然な流れに任せていい」という東洋哲学の知恵は、肩の力を抜いてくれる大きな支えになりました。
自然体で向き合うことが、実はチーム全体の成果にもつながる。そんな実感を、今は持てるようになっています。
-

【医療マネジメント認定士】1−3セルフケアを学んで気づいた「自分を整える5つの視点」
-


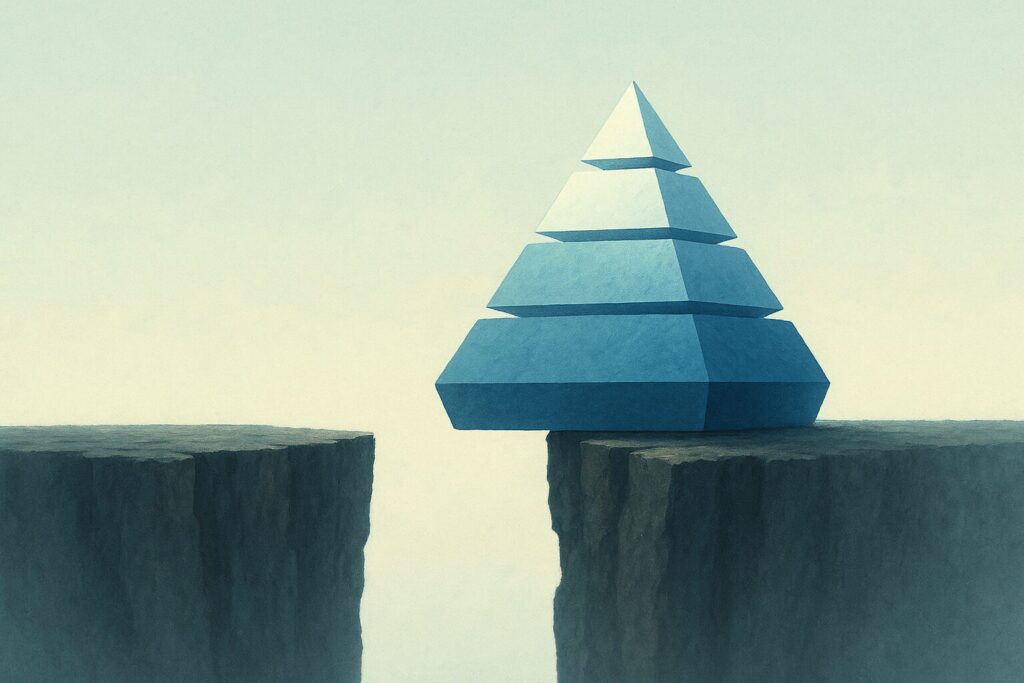
【医療マネジメント認定士】1−1 ケアの本質と「欲求」の土台を理解する
-



【現場の悩みを解決!】医療従事者こそ学ぶべき「医療マネジメント認定士」とは?
-



【2025年のドジャースの課題に学ぶ】中間管理職が活かせる5つのポイント
-



感情の“沼”にハマる前に…3分でできる気持ちのリセット術
-



【中間管理職が不安なあなたへ】「流れに任せる」ことで開けたキャリアの話
-



業務改善を成功させる視点とは?「簡単に働く」ための考え方
-


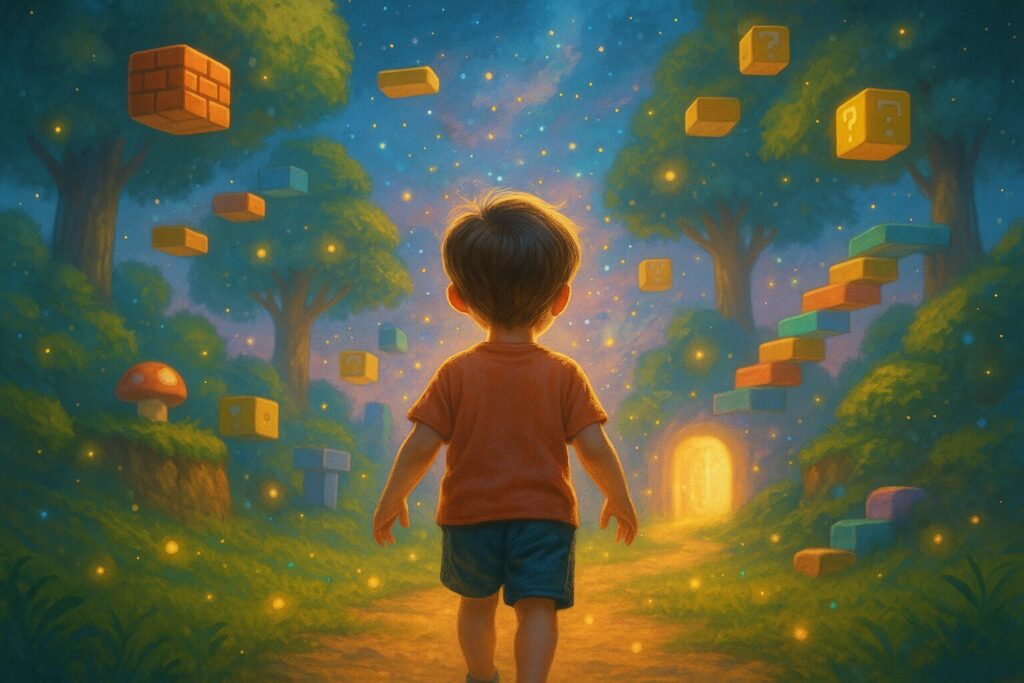
「子どもが言うことを聞かない…」その悩み、”遊び”で解決できるかも
-


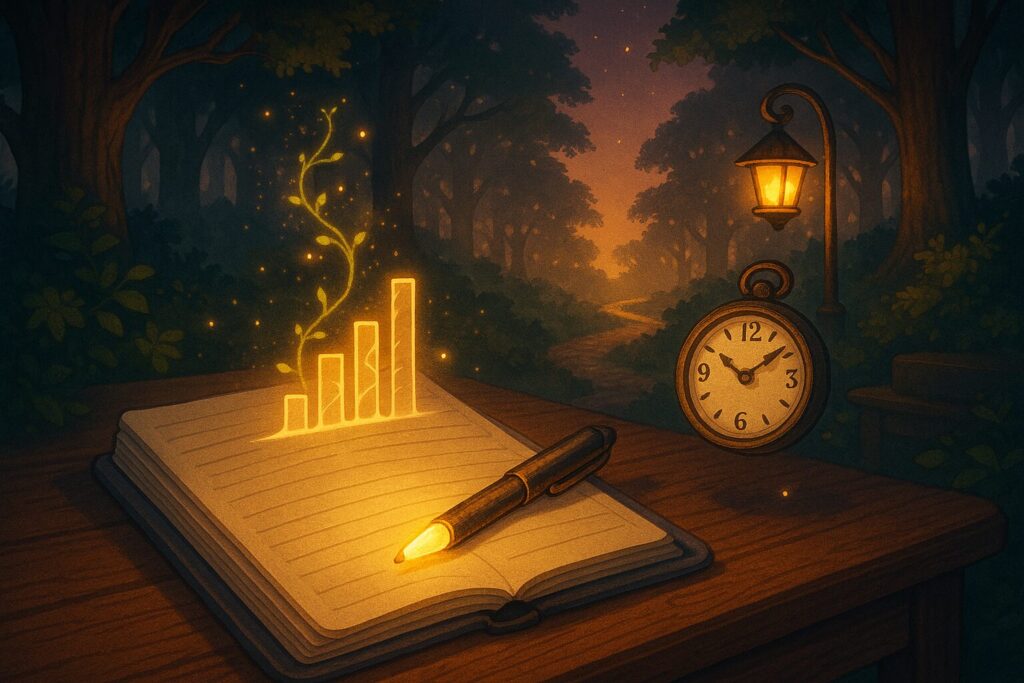
愚痴が出そうなときこそ、自分の行動を記録して整える