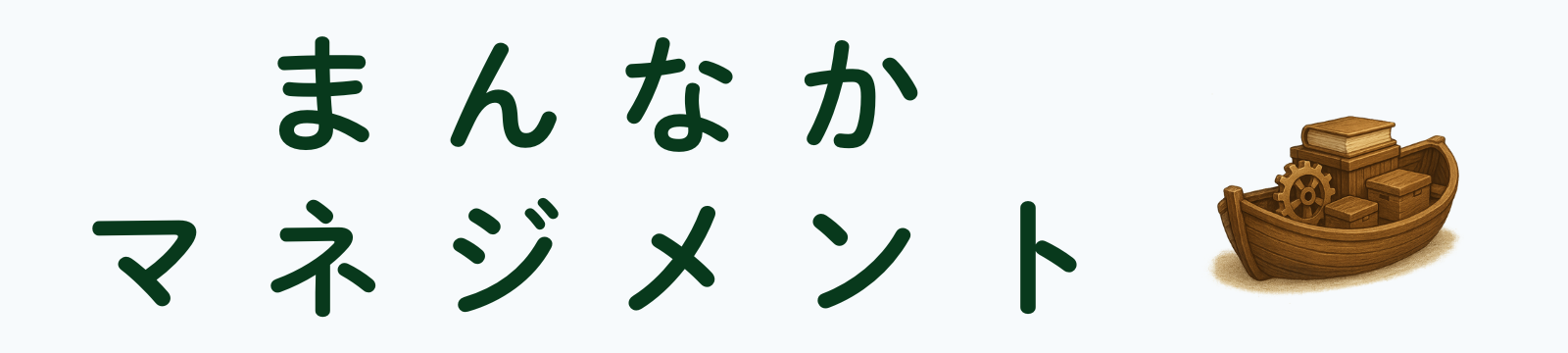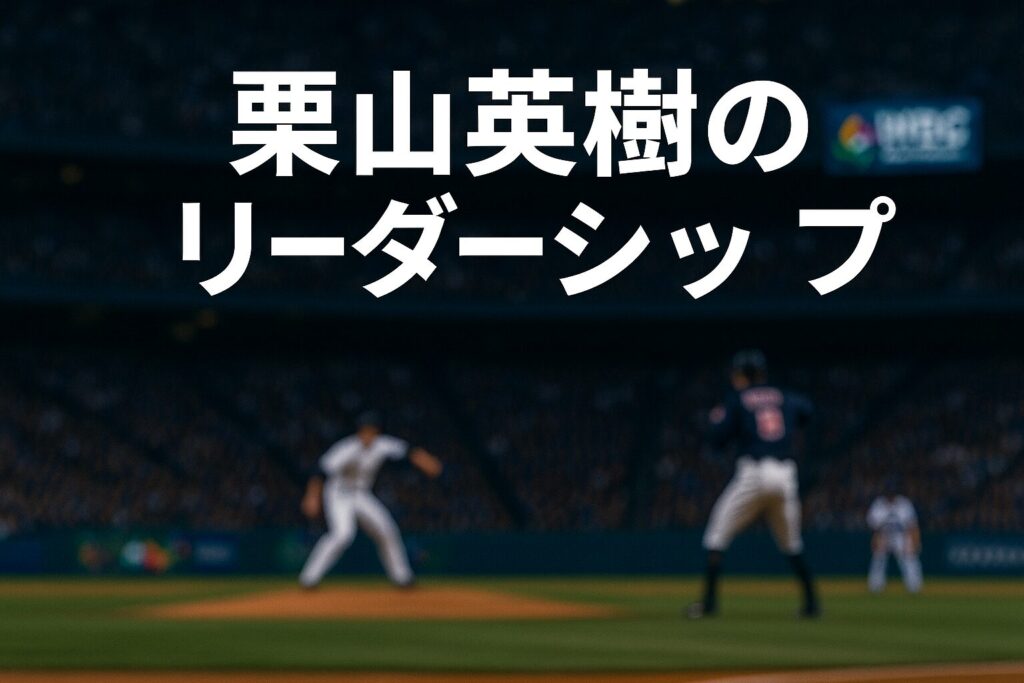はじめに|「言ったはず」がすれ違いを生む
「確かに伝えたのに、なぜか動いてくれない」
「何度言っても理解されていない気がする」
管理職として働いていると、「伝えたつもりなのに伝わっていない」という場面に何度も遭遇します。
これは指示の出し方が悪いのではなく、「伝えること」と「伝わること」は別物であるということを知らないまま進んでしまうことが原因です。
この記事では、伝えたつもりを防ぐために押さえておきたい3つのポイントと実践的な工夫を紹介します。
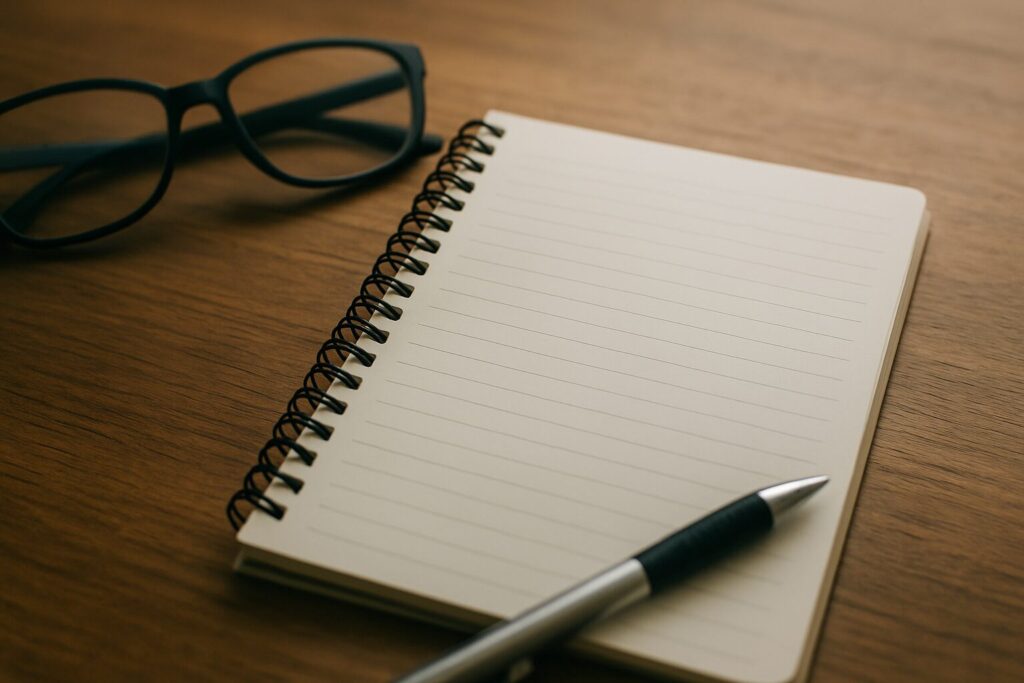
なぜ「伝えたつもり」になってしまうのか?
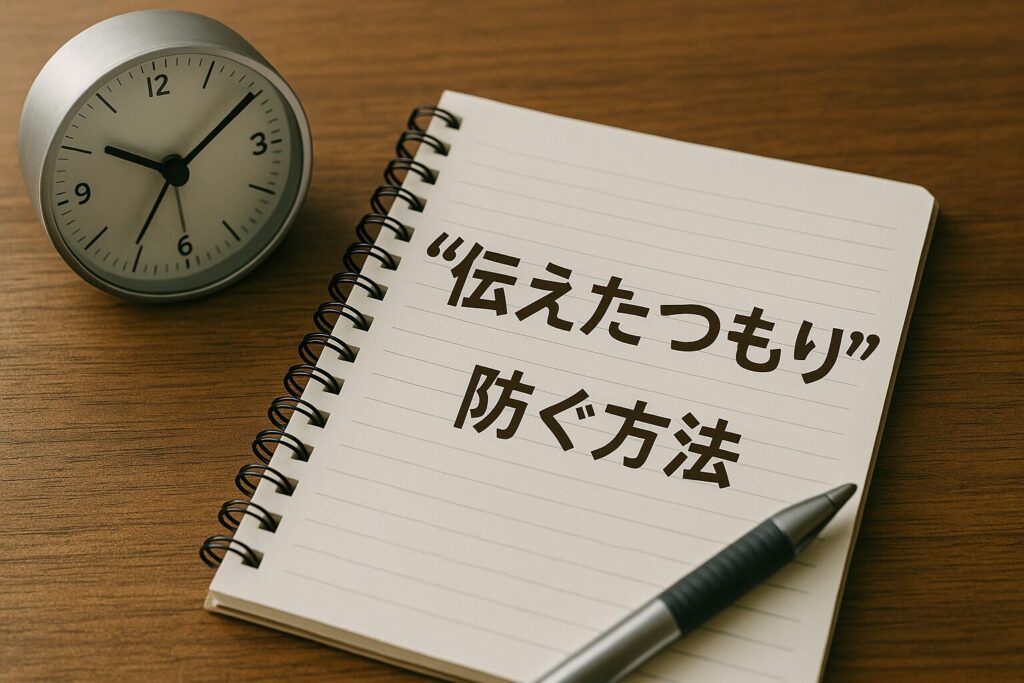
1. 自分の頭の中では整理できている
管理職は、組織全体の動きや流れをある程度把握しながら仕事を進めることに慣れています。
そのため、日常的に多くの判断や情報処理を「頭の中」で済ませることができます。これは一種のスキルであり、強みでもあります。
ただし、その頭の中で完結してしまった情報を、相手が同じように理解してくれるとは限りません。
たとえば、自分は「○○の資料は去年の形式を使えばいい」と思っていても、それを言葉にせずに「例の資料、お願い」とだけ伝えてしまう。
部下からすれば、「形式は自由でいいのか?」「何のために使うのか?」など、判断に迷いが生じます。
このように、“頭の中の情報を省略してしまう”ことが、伝達のズレを生み出す大きな要因です。
また、管理職としての経験が長くなるほど、「ここは言わなくてもわかるだろう」「察して動いてくれるだろう」といった無意識の期待が強くなりがちです。
しかし、それはあくまで自分の視点での判断であり、受け手にとっては「何をどうしたらいいか」が不明確なままになってしまうこともあります。
とくに新入社員や異動してきたばかりのスタッフにとっては、周囲の“暗黙の了解”そのものが未知のものです。
「あえて説明しなくてもわかるだろう」という思い込みが、思わぬ誤解や遠回りを生むのです。
2. 相手が理解しているかを確認していない
指示や依頼を伝えたあと、「わかった?」と聞いて「はい」と返されたとき、ついそれだけで“伝わった”と判断してしまいがちです。
しかし、これは非常にあいまいな確認方法です。
なぜなら、「はい」は必ずしも「完全に理解しました」という意味ではないからです。
職場の上下関係や遠慮のある人間関係のなかでは、「実はよく分かっていないけど、質問するのは気が引ける」「聞き返したら怒られるかも…」と考えて、わからないままやり過ごそうとする場面が少なくありません。
あるいは、「何となくこういうことかな?」という自己解釈のまま動いてしまい、結果として求めていたものとズレた成果物が出てくる、ということも起こります。
実際の現場では、「あのときは分からなかったけど、今さら聞きづらくて…」という部下の本音を耳にすることもあるのではないでしょうか。
このように、「相手が理解したかどうかの確認を怠る」ことは、“伝えたつもり”を生む直接的な原因になります。
「話した=伝わった」ではない。
「返事をした=理解した」でもない。
伝えた側が“伝わったことの確認”まで責任を持つことが、実は最も重要な工程なのです。
伝え方を整えるチェックリスト
「伝えたつもり」を防ぐためには、伝える側が伝え方の基本を押さえているかを見直すことが大切です。
以下のチェックリストをもとに、普段の指示出しや連絡を自己点検してみましょう。
5つの確認ポイント
- 指示に「期限」が明確についているか
→「できるだけ早く」ではなく「○日○時まで」と伝える - 「誰が、何をするか」がはっきりしているか
→グループ宛ではなく個人単位で明示すると伝わりやすい - 相手の理解度を確認しているか
→「わかった?」ではなく「今どう受け取った?」と問い返す - 口頭+文字でダブル確認しているか
→メモ・メール・チャットなどで要点を残す習慣をつける - 相手の性格や理解スピードを考慮しているか
→経験が浅い人には丁寧に。ベテランには要点のみ。
このように、相手視点での伝達設計を意識するだけでも、伝達ミスは大きく減らすことができます。
「伝えたつもり」を防ぐ3つの実践ポイント
① 指示は「3W1H」で伝える
Who(誰に)
What(何を)
When(いつまでに)
How(どのように)
この4要素を意識するだけで、指示はぐっと明確になります。
たとえば:
✕「会議の準備、お願いね」
→ 何を準備する?いつまで?誰が何をやるのか不明
〇「来週火曜の会議資料を、金曜までにAさんと一緒にまとめてほしい。去年のフォーマットを参考にして」
→ 具体的にすべてが明示され、誤解の余地が減る
②「オウム返し」で確認する
相手に「今の話、どう理解した?」と聞き返してもらうことで、双方の認識ズレをその場で確認できます。
この方法はシンプルですがとても効果的で、「自分の言葉で言い直してもらう」ことで、理解度が可視化されます。
③ 文字で補足する
口頭で伝えるだけでなく、メール・チャット・メモなど、書き残す習慣を持ちましょう。
特に忙しい現場では、時間が経つと内容を忘れたり、言った言わないのトラブルにもつながります。
短くても「要点を文字で残す」ことで、相手に安心感も与えられます。
よくあるNGパターンとその改善例
| NGな伝え方 | 改善例 |
|---|---|
| 「これ、いい感じに仕上げて」 | →「この資料を5分以内で話せるように要点をまとめて」 |
| 「あとでやっておいて」 | →「今日中にやってほしい。16時までに確認したい」 |
| 「これくらいならわかるでしょ?」 | →「初めてだから補足するね。ここが重要なポイントです」 |
まとめ|伝えるのではなく、伝わる仕組みを作ろう
「伝えたつもり」が引き起こすのは、単なるミスではなく、信頼関係のゆらぎです。
管理職としての伝達力は、「どれだけ話したか」ではなく、「どれだけ相手に伝わったか」で決まります。
- 3W1Hを意識した具体的な伝え方
- 相手の理解を確認する習慣
- 書き残す工夫と聞き方の柔らかさ
これらを積み重ねることで、「言ったはず」ではなく、「きちんと届いた」を実感できる日常が生まれます。
まずは今日のひとつの指示から、“伝える”を少しだけ丁寧にしてみましょう。
/