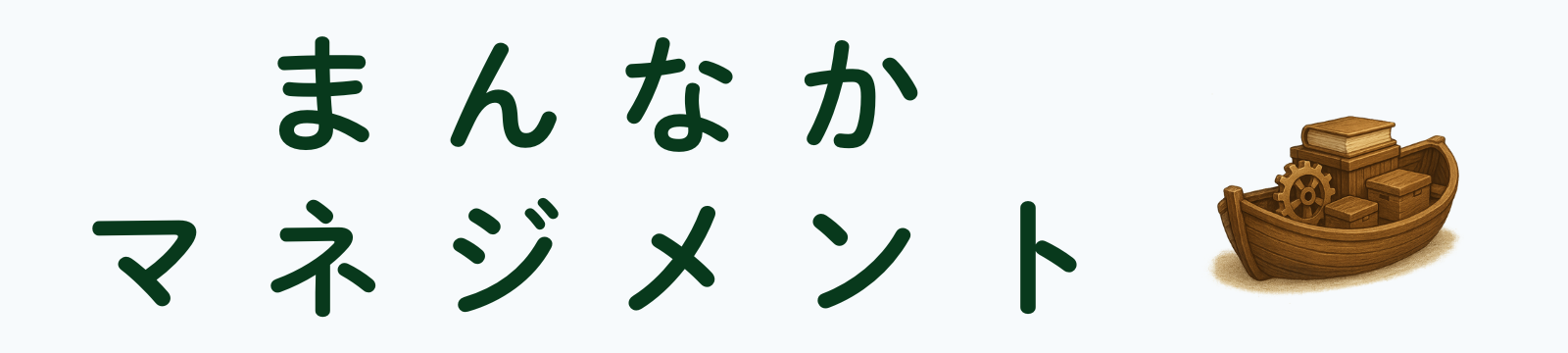介護老人保健施設(老健)において、生産性向上は避けて通れないテーマになりつつあります。
特に、ICT機器や介護ロボットの導入が注目されるなか、「効率化」が叫ばれることが増えてきました。
私自身、病院で作業療法士として長年勤めたのち、老健に異動してからこの“生産性”という言葉を初めて介護現場で知りました。
厚労省も生産性向上について発信しています。
そして感じたのは、今、目の前の業務を見直していなければ、いくら機械を導入しても本当の意味では活かされないのでは?という疑問です。
この記事では、老健におけるICT導入と生産性向上の現実を踏まえつつ、導入前にやるべき“今できる改善”について掘り下げてみます。
なぜ今、老健に「生産性向上」が求められているのか?
老健では、医療と介護の中間地点として、生活支援と在宅復帰支援の両立が求められています。
一方で、慢性的な人手不足、複雑化する業務、職員の業務負担の偏りといった問題が積み重なっています。
こうした状況から、「もっと効率的に運営するにはどうすればいいか?」という問いが強まり、生産性向上というキーワードが現場でも取り上げられるようになってきました。
ICT導入で本当に老健の業務効率は上がるのか?
ICT・介護ロボット導入のメリットとしては、以下のような点がよく挙げられます。
- 記録の自動化で事務負担が軽減される
- 見守り支援により夜間対応が安定する
- 移乗介助ロボットで身体的負担が減る
しかし現場の声に耳を傾けてみると、「操作が難しくて、現場で誰も使いこなせない」「結局手作業に戻った」「導入の目的が曖昧でスタッフの負担が増えた」といった声も少なくありません。
これらに共通するのは、“技術をどう使いたいのか”が明確になっていないまま導入されている、ということです。
高齢な職員が多い現場だとデジタルに疎い場合も多いので、導入しても逆に負担感が増す可能性が考えられます。
老健でICT導入の前にやるべき「今できる改善」とは?
私は、老健の業務改善を考えるとき、高価な機械よりもまず現場を整えることが先では?と考えるようになりました。
たとえば、以下のようなことから始められるかもしれません。
- 申し送りや記録のテンプレート化で、情報のばらつきをなくす
- 職員の動線や時間の使い方を見える化して、ムダを減らす
- OJTで“やり方”だけでなく“なぜやるのか”を一緒に伝える
これらはICTを導入しなくてもできる工夫であり、こうした現場の土台があってこそ、ICTも初めて“使えるもの”として活かされるのではないかと思います。
というのも、実際の現場で過ごしていると「生産性向上」の言葉だけが一人歩きして、空いた時間、人材を何に使うのかが全く決まっていないように思えたのです。
老健の「生産性向上」は小さな工夫の積み重ね
派手な改革をしなくても、毎日の業務を少しずつ見直していくだけで、現場は確実に変わっていきます。
- 記録の流れを変えるだけで、職員のストレスが減る
- ケアの声かけを少し意識するだけで、利用者の反応が変わる
- チームで課題を話し合う時間を設けるだけで、風通しが良くなる
技術導入に頼る前に、こうした“下地”を整えておくことこそ、長く続く改善の鍵になると感じています。
でも、この現時点の業務を見直すために技術を導入するのは良いことだと思っています。
例えばchatGPTで現在の業務について多角的な視点で評価してもらったり、新たなアイデア出しを手伝ってもらったり。
モノも大切ですが、ヒトの意思が変わるだけでも大きな効果が生めるのではないかと思います。
おわりに:老健の生産性向上は「今、目の前」から始まる
老健に異動してから実感しているのは、生産性向上は未来の話ではなく、「今の働き方」を見直すことから始まる、ということです。
ICTやロボットがどれほど進化しても、使うのは人。
だからこそ、今できることをどれだけやれているかで、将来的な成果は大きく変わるはずです。
もし現場で「これはムダかも」と感じていることがあれば、それがすでに最初の改善の種なのかもしれません。
小さなことを解決するためにAIなどを活用してみてはいかがでしょうか。
-

【多忙な管理職の救世主】寝るだけで疲れをリセット!シャクティマットの驚きの効果
-


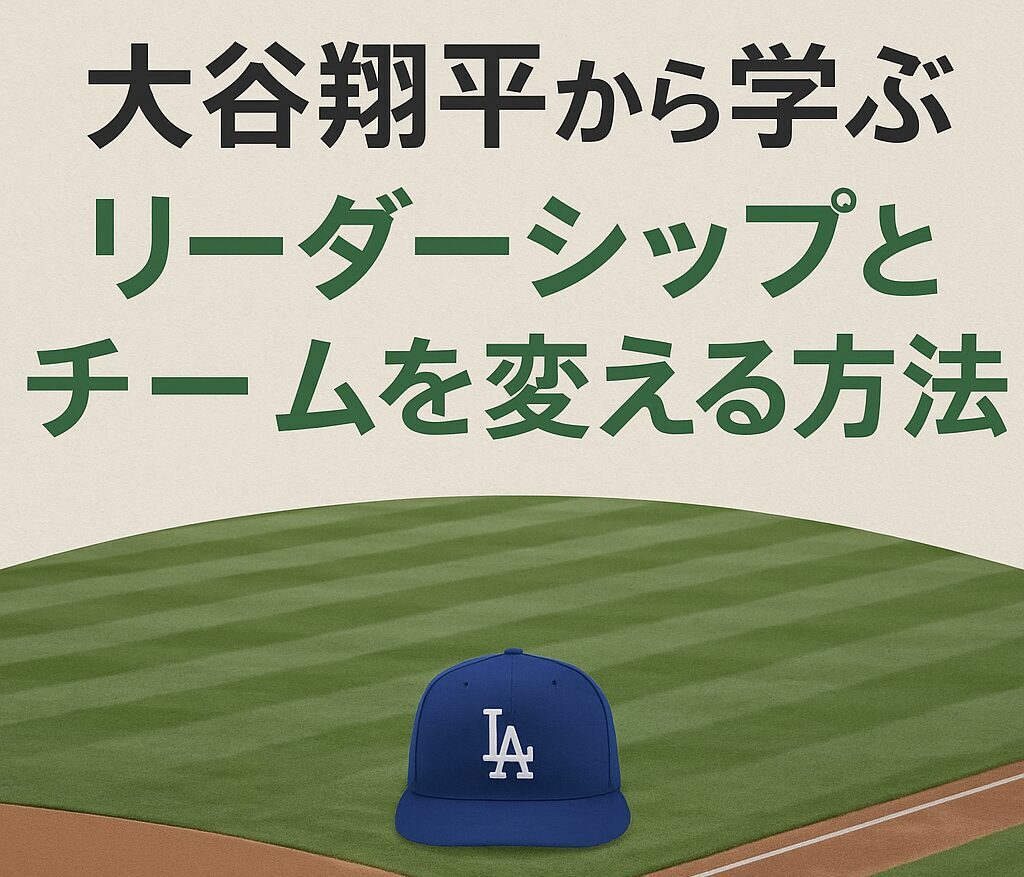
大谷翔平に学ぶリーダーシップで人生とチームを変革する方法
-



【アンガーマネジメントと6秒ルール】管理職の怒りの付き合い方
-



【完全ガイド】MBTI16タイプ別リーダーシップの特徴と活かし方
-



【希少なリーダーシップ】INFJ型が管理職で輝く!共感と理想を力に変える秘訣
-



シャクティマット半年レビュー:中間管理職のストレス対策として「買う価値はある?」
-



INFJのリーダーシップとは?理想と共感で導く“提唱者型”の強みと課題
-



ISTPのリーダーシップ:静かに動き、現場を支える“職人型”の実践力
-



【急変対応に自信がつく!】急性期ケア専門士資格ガイド2025