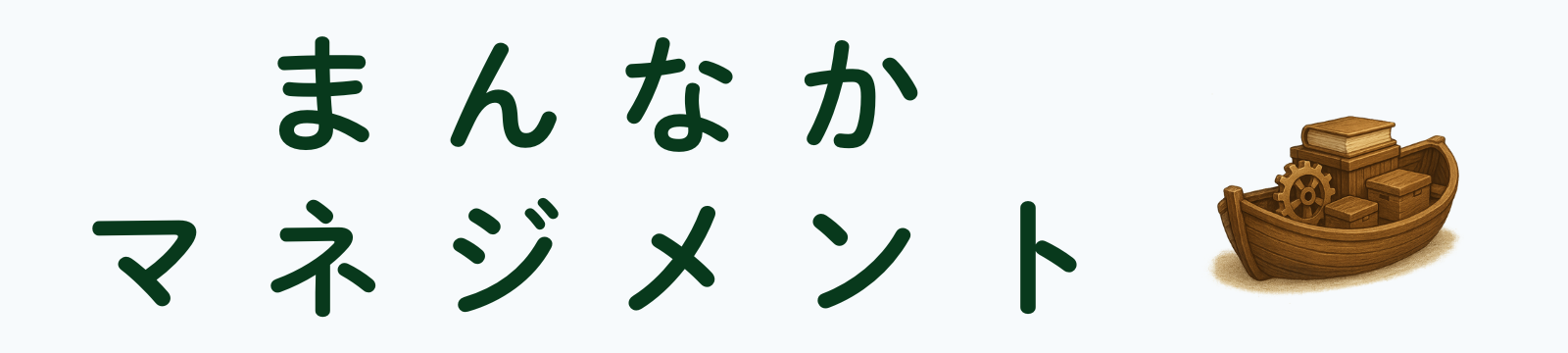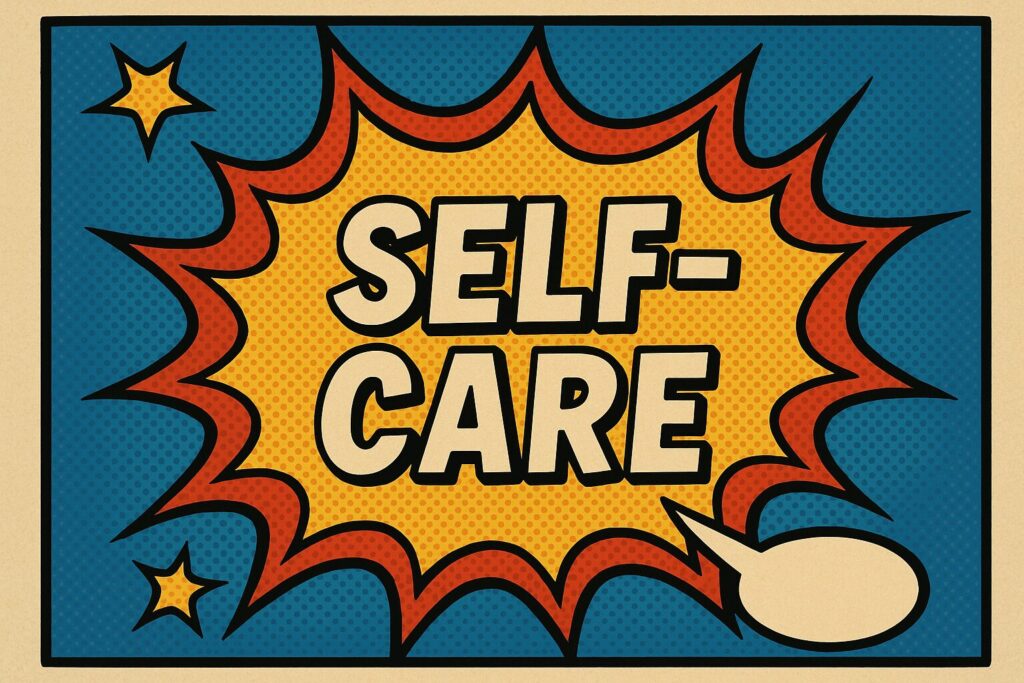現場は今日も忙しい。スタッフは疲れ気味、自分もいつも時間に追われている。それでも「利用者のために」と頑張ってしまう――。そんな毎日を過ごしていませんか?
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。
その努力、本当に必要ですか?
そして、それはあなた一人で背負うべきものですか?
管理職として現場を任されて数年。
私が業務改善に取り組む中で気づいたのは、「もっと頑張る」ではなく、「もっとラクに働ける方法を考える」ことの大切さでした。この記事では、医療・介護の現場で“がんばりすぎない業務改善”を実現するための視点と実践法を、私自身の経験も交えてお伝えします。
なぜ「簡単に働く」視点が必要なのか
「もっと良いケアを提供したい」「利用者の満足度を上げたい」――そう思うのは、医療・介護職として当然のことです。私も現場に入った頃は、常に“利用者のため”を軸に仕事をしてきました。しかし、管理職になってから気づいたのは、「利用者満足」を追い求めるだけでは、現場の働きやすさや業務効率には限界があるということです。
現場が回らない、残業が減らない、スタッフが疲弊している――これらの課題の多くは、「現場の頑張り」に依存している状況に起因しています。つまり、“より良く”よりも“よりラクに”という視点を加えないと、持続可能な改善は難しいのです。
特に管理職である私たちは、現場での実務だけでなく、「全体の流れ」や「仕組みそのもの」に目を向ける役割があります。たとえば、同じ業務でも「Aさんだと早いけどBさんだと時間がかかる」というケース。これは仕組みが人に依存している状態です。こうした属人化をなくし、誰でもスムーズに業務を進められるようにすることも、「ラクに働く」ための重要な視点です。
つまり、管理職としての視座を「利用者視点+現場の持続可能性」に広げることで、業務改善の質は格段に上がるのです。
現場にありがちな「がんばりすぎ改善」の落とし穴
「困っているなら、私がやるよ」
「これくらい、頑張れば何とかなるはず」
現場で働く私たちは、こうした“善意の努力”で多くの問題を乗り越えてきました。でも、これを業務改善の手段として繰り返していると、いずれどこかで限界が来ます。
私の体験ですが、かつてチーム内でトラブルが多発し、スタッフ同士の連携もうまくいっていない時期がありました。その頃、私は毎日誰よりも早く出勤し、トラブル対応や記録のチェック、資料作成を一人でこなしていました。一時的にはうまくいっていたように見えましたが、私の疲労は限界に近づき、周囲も「結局〇〇さん(私)に頼ればいい」という空気になっていったのです。
これが、「頑張りの延長による改善」が危険な理由です。一人に負荷が集中し、他のスタッフの成長機会も奪ってしまう。しかも、仕組みは変わらないので、本人が倒れればすべてが止まります。
さらに、「忙しいのは当たり前」という前提が現場に根付いてしまうと、改善のアイデアすら出にくくなります。「本当はやめた方がいいけど、仕方ないよね」というあきらめが、組織に蔓延してしまうのです。
だからこそ、管理職がまずその思い込みを疑う必要があります。「本当にこの業務、今の形でやる必要があるのか?」と問いかけることが、抜本的な改善への第一歩になります。
「楽に働く」ための業務改善マインド3選
① 仕組みで解決する
人の努力ではなく、仕組みに任せる。チェックリストやテンプレート、デジタルツールの活用で業務を標準化することで、誰でも同じレベルでこなせるようになります。
② やらないことを決める
「これは本当に必要か?」と問い直す勇気が大切です。ルーティン化している業務を見直し、やめられることを一つずつ減らしていきましょう。
③ 属人化をなくす
「〇〇さんしかできない仕事」はチームにとってリスクです。情報共有や業務分担を見直し、誰が休んでも回る状態を目指します。
実際に行った業務改善の例とその効果
私が職場で取り組んだのが書類業務の見直しでした。現場では、同じ内容を複数の様式に記載する“二重入力”や、入力ミスといった問題が頻繁に発生していました。
これにより、スタッフの心理的負担だけでなく、ミスによる業務のやり直しも増えていたのです。
そこで、これらの書式を洗い出し、情報の一元化と記録フローの再構築を行いました。具体的には、初回入力時に必要な情報をすべてカバーできる統合フォームを作成し、そこから他の書類への自動転記やコピペが可能なフォーマットに変更。さらに、入力ミスが起こりやすい箇所にはプルダウンや選択肢を導入し、記入ミスを予防しました。
この見直しにより、記録業務にかかる時間が平均で1日あたり約45分短縮され、残業の削減にもつながりました。
もう一つ大きな成果を感じたのが、スタッフの役割分担の見直しです。
以前は「全員が何でもできる体制」を目指していましたが、それではかえって責任の所在が曖昧になり、仕事が偏る傾向がありました。そこで、「得意なこと・関心のあること」を基準に役割を再編。たとえば、情報整理が得意なスタッフには記録のチェックを、明るく対人スキルの高いスタッフにはグループワークの司会役や他スタッフの個性の引き出し役に。
その結果、本人のモチベーションが上がり、「あの仕事、私やるよ」といった自発的な行動や声かけが増加。以前は連携に課題があったメンバー間でも、自然とフォローや助け合いが生まれるようになり、チームの空気が大きく変わったと実感しています。
このように、「もっとラクに働く」ための改善は、表面的な効率化にとどまらず、チーム全体の心理的安全性や自律性の向上にもつながるのです。
まとめ|視点を変えれば、働き方はもっとラクになる
「業務改善=新しいことを始める」ではなく、「今あるムダを減らす」ことから始まります。
管理職として大切なのは、目の前の忙しさに埋もれず、「どうすればもっとラクに働けるか?」という視点を持ち続けること。
まずは明日、「やめられること」を1つ探してみてください。
それが、チーム全体の働き方を変える最初の一歩になるかもしれません。
-

【医療マネジメント認定士】1−3セルフケアを学んで気づいた「自分を整える5つの視点」
-


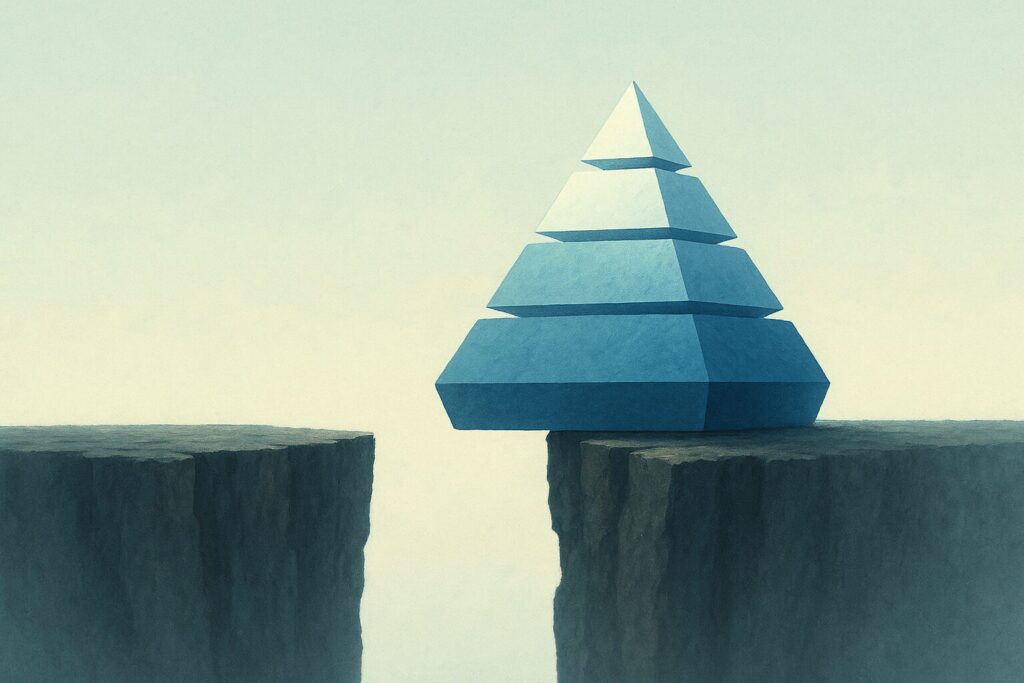
【医療マネジメント認定士】1−1 ケアの本質と「欲求」の土台を理解する
-


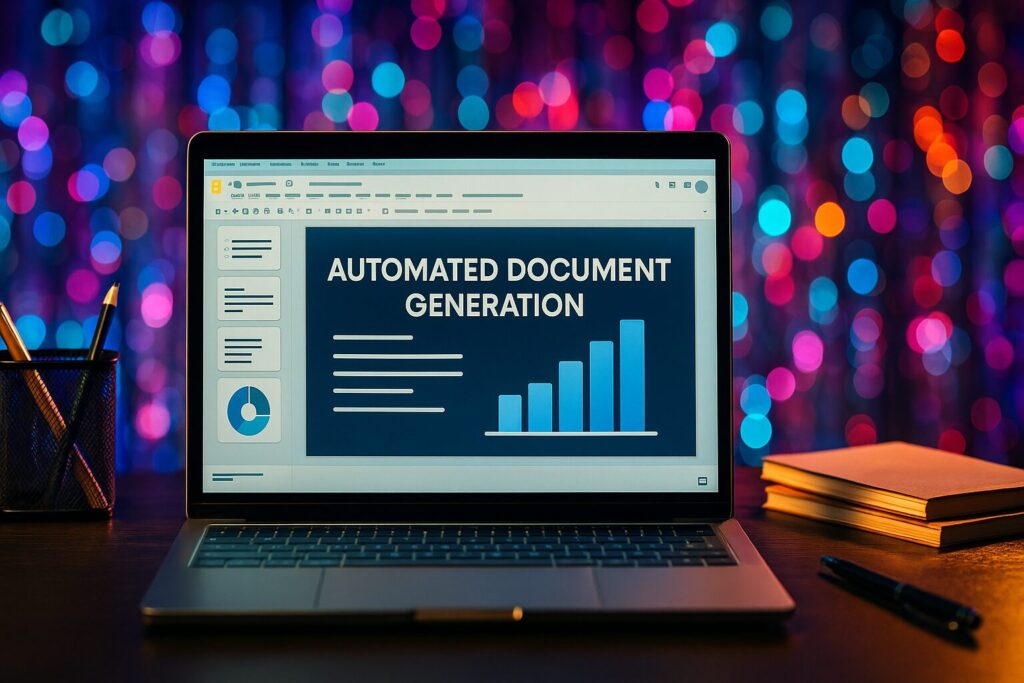
現場の時間を取り戻す。リハビリ中間管理職が出会った「まじん式Flash (V3)」という資料作成の革命
-



【現場の悩みを解決!】医療従事者こそ学ぶべき「医療マネジメント認定士」とは?
-


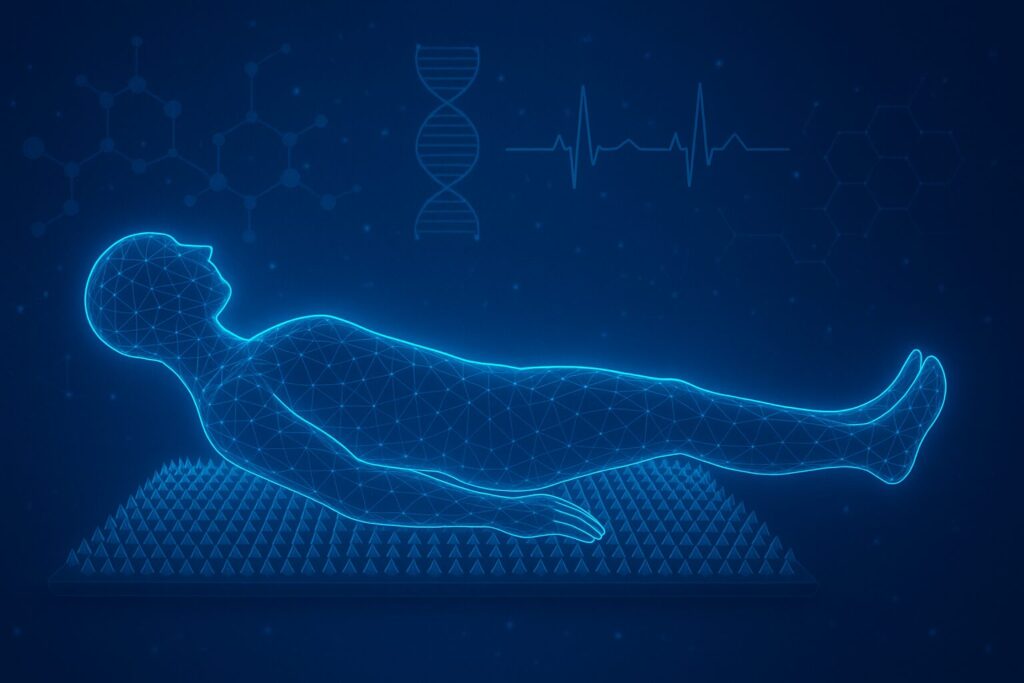
初心者必見!シャクティマットの痛みを軽減する方法
-



【2025年のドジャースの課題に学ぶ】中間管理職が活かせる5つのポイント
-



会議で意見が言えない人へ|嫌われずに発言できる3つの思考法
-


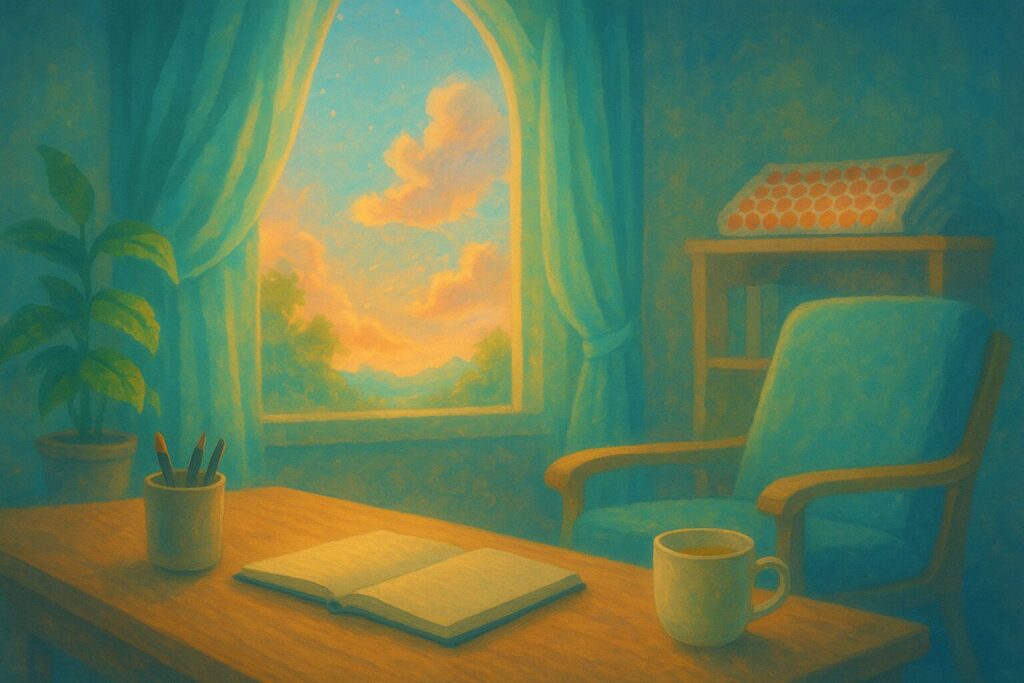
【中間管理職のストレス管理術】罪悪感なく休める「マイクロレスト」とセルフコンパッション習慣
-



感情の“沼”にハマる前に…3分でできる気持ちのリセット術