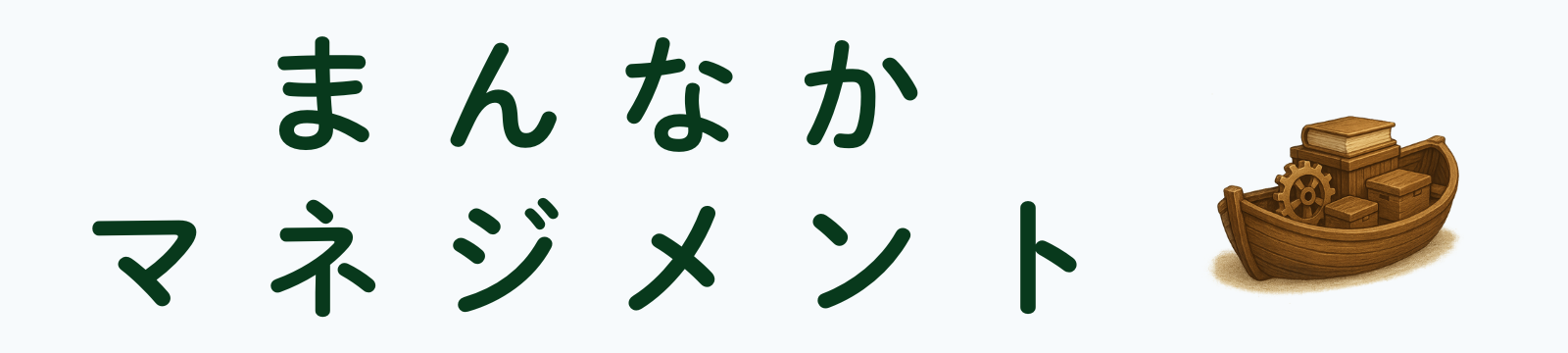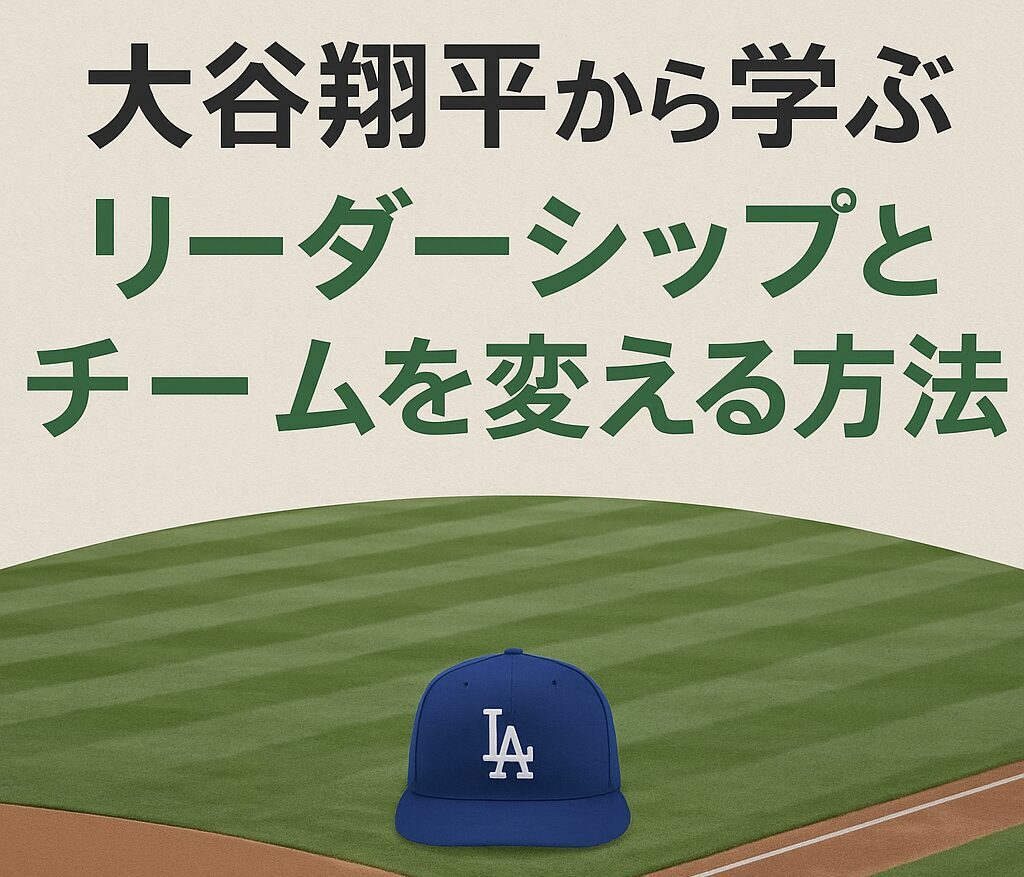「管理職に求められるスキルって、実際どこから学べばいいのかわからない」
そんな不安を感じながら、毎日の業務に追われていませんか?
初めて管理職になった方や、マネジメントに苦手意識を持つ方にとって、「マネジメントスキル」という言葉は漠然としていて、とても広く感じられるものです。
この記事では、マネジメントスキルの基本構造と階層別の違い、さらにスキルアップのために意識したい具体的な方法について、順を追ってご紹介します。
少しずつ一緒に整理していきましょう。
よくある悩みとつまずき
管理職に就いたばかりの人がよく口にするのが「結局、何を求められているのかわからない」という声です。
プレイヤー時代は自分の業務に集中していれば良かったのに、管理職になると急に「部下育成」「チームマネジメント」「意思決定」など、多くの役割を担うことになります。
研修を受けても現場では通用しない、目の前のトラブル対応で手一杯、誰にも相談できない——そんな状況に陥りがちです。
私自身も、最初に管理職になったときは、部下との距離感や会議の進行、業務配分に悩み、何を優先すべきか分からなくなっていた時期がありました。
解決のヒントと考え方
まず知っておきたいのが、「マネジメントスキルは一種類ではない」ということです。
アメリカの経営学者カッツが提唱した「カッツモデル」では、管理職に必要なスキルを以下の3つに分類しています。
- テクニカルスキル(業務遂行能力)
- ヒューマンスキル(対人関係能力)
- コンセプチュアルスキル(概念化能力)
たとえば、係長やチームリーダーには、部下との距離が近いため、テクニカルスキルやヒューマンスキルの比重が大きくなります。
一方で、部長やゼネラルマネージャー層になると、組織の方向性を定めたり、経営陣と連携したりと、よりコンセプチュアルな視点が求められます。
さらに、マネジメントスキルは画一的なリストで測れるものではありません。
自社のビジョンや組織風土、管理職に期待する役割によって、必要なスキルは変わってきます。
たとえば「挑戦を重視する会社」では失敗を許容するマネジメント、「安定を求める会社」では丁寧な進捗管理が重視されるかもしれません。
スキル定義のステップとしては、
- 企業の目指す組織像を明確にする
- それに基づく管理職の役割を言語化する
- 必要な行動を洗い出し、必要スキルに落とし込む
という流れで設計すると、自社にとって本当に必要なスキル像が見えてきます。
少しずつ前に進むために
マネジメントスキルは「知識を詰め込む」だけでは身につきません。
実際の現場で「試して、振り返って、改善する」プロセスが何より重要です。
たとえば、ある日の会議で部下の意見をしっかり聞いてみる、
ちょっとした成功体験を言語化して共有する、
あるいは、自分の考えをフィードバックとして伝える——
こうした「小さな実践」が積み重なって、自信とスキルになります。
また、上司や同僚からのフィードバックを受けることも、自分の視点を広げる大切な機会です。
自分では気づかなかった長所や改善点を知ることができ、成長の方向性が明確になります。
360度評価や他部署との対話も有効な手段です。
さらに、eラーニングやマネジメント研修など、OJTでは得られない体系的な知識を取り入れることで、視野を広げることができます。
重要なのは、「学び続ける姿勢」を持つことです。
まとめ
管理職に必要なマネジメントスキルは、一言で言えるほど単純ではありません。
しかし、全体像を把握し、役割や組織に応じたスキルを意識することで、着実に育てていくことができます。
完璧である必要はありません。
まずは、今日できる小さな一歩から始めましょう。
あなたが積み重ねた経験と学びが、明日のチームをより良くしていくはずです。